福島県双葉町は、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故によって全町避難を余儀なくされました。長い避難期間を経て2020年3月に一部区域の避難指示が解除され、現在、町の復興・再生に向けた取り組みが本格化しています。その復興計画の中核には、SDGs(持続可能な開発目標)の理念が組み込まれ、単なる復旧ではなく、より強靭で持続可能な未来のまちづくりが進められています。本記事では、双葉町が進めるSDGsを基盤とした独自の復興の取り組みを紹介します。
震災からの復興とSDGsの統合
2011年3月11日の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故は、双葉町に壊滅的な被害をもたらしました。全町民約7,000人が避難を余儀なくされ、9年以上にわたって町全体が避難指示区域となっていました。
避難指示解除と復興の新たなスタート
2020年3月4日、JR双葉駅周辺の一部区域(町域の約5%)の避難指示が解除され、双葉町は復興への新たな一歩を踏み出しました。その後、2022年6月には特定復興再生拠点区域(町域の約15%)の避難指示が解除され、住民の帰還が可能になりました。
双葉町の避難指示解除の進展
2011年3月
東日本大震災と福島第一原子力発電所事故により全町避難
2017年9月
特定復興再生拠点区域復興再生計画認定
2020年3月4日
JR双葉駅周辺の一部区域(町域の約5%)の避難指示解除
2022年6月
特定復興再生拠点区域(町域の約15%)の避難指示解除、住民の帰還開始
現在〜未来
SDGsを基盤とした持続可能なまちづくりの推進
SDGsを取り入れた復興計画
双葉町は「双葉町復興まちづくり計画(第二次)」において、SDGsの理念を取り入れた復興ビジョンを掲げています。この計画では、「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念に沿って、環境・社会・経済の三側面から持続可能なまちづくりを目指しています。
特に以下のSDGs目標との関連が強い取り組みが進められています:
- 目標7:エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
- 目標11:住み続けられるまちづくりを
- 目標13:気候変動に具体的な対策を
- 目標15:陸の豊かさも守ろう
- 目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
環境に配慮した持続可能なインフラ整備
双葉町の復興計画では、環境に配慮した持続可能なインフラ整備が重要な柱となっています。
災害に強いまちづくり
東日本大震災と津波の教訓を活かし、以下のような災害に強いインフラ整備が進められています:
- 海岸防災林や防潮堤の整備
- 高台への避難路の確保
- 公共施設の耐震化と多重防護
- 災害時の電力確保のためのマイクログリッドシステムの検討
再生可能エネルギーの推進
双葉町は、原子力発電所事故の経験を踏まえ、持続可能なエネルギー政策として再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています:
- 町内の遊休地や除染後農地を活用した太陽光発電事業
- 福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)との連携による水素エネルギーの活用検討
- スマートコミュニティ構想の推進
福島県が掲げる「福島新エネ社会構想」と連携し、福島県を再生可能エネルギー先駆けの地とする取り組みに双葉町も参画しています。
環境修復と生態系の再生
原子力発電所事故による環境への影響に対処するため、以下の取り組みが行われています:
- 除染作業による放射線量の低減
- 森林の再生と生態系回復プロジェクト
- 河川や海岸の環境モニタリングと保全活動
- 生物多様性の確保に向けた調査研究
人に優しい包括的な社会づくり
双葉町の復興は、インフラの再建だけでなく、帰還する住民や新たな住民が安心して暮らせる社会づくりにも重点を置いています。
医療・福祉サービスの再構築
長期避難により分断されたコミュニティの再構築と、特に高齢者や障がい者など配慮が必要な方々への支援を重視しています:
- 双葉町の中心部に設置された「ふたば医療センター附属病院」を核とした医療体制の整備
- 遠隔医療サービスの導入検討
- 介護・福祉サービスの段階的な再開
- 心のケアを含む健康サポート体制の構築
教育と文化の再生
次世代を担う子どもたちの教育環境の整備と、双葉町の文化・伝統の継承にも力を入れています:
- 双葉町立学校の再開準備
- ICTを活用した先進的な教育環境の整備
- 避難先で学ぶ子どもたちへの継続的な支援
- 伝統行事や文化の保存・継承活動
コミュニティの再構築
避難により分散した住民のつながりを再構築し、新たなコミュニティづくりを支援しています:
- 交流拠点「双葉町産業交流センター」の設置
- コミュニティスペースの整備
- オンラインも活用した町民交流の促進
- 多様な世代が参加できるまちづくりワークショップの開催
持続可能な産業・経済の復興
双葉町の経済的な持続可能性を確保するため、新たな産業の創出と既存産業の再生が図られています。
イノベーション拠点の形成
「福島イノベーション・コースト構想」の一環として、双葉町でも新たな産業創出の取り組みが進められています:
- 廃炉関連産業の集積
- 再生可能エネルギー関連ビジネスの育成
- ロボット技術など先端技術の開発・実証
- 研究機関や企業の誘致
農林水産業の再生
双葉町の基幹産業であった農林水産業の再生に向けた取り組みも行われています:
- 試験栽培等による農地の再生
- 放射性物質の影響を受けない安全な農産物生産システムの研究
- スマート農業の導入検討
- 「ふたばブランド」の確立に向けた取り組み
観光・交流人口の拡大
震災と原発事故の経験を教訓として伝えるとともに、新たな観光資源の開発も進められています:
- 震災・原発事故の記憶を伝える「東日本大震災・原子力災害伝承館」との連携
- 双葉町の歴史や文化を伝える資料館の整備
- 交流人口・関係人口の拡大に向けた取り組み
- 教育旅行の誘致
双葉町の復興とSDGs目標の対応
| SDGs目標 | 双葉町の主な取り組み |
|---|---|
| 目標7: エネルギーをみんなに、そしてクリーンに |
|
| 目標11: 住み続けられるまちづくりを |
|
| 目標13: 気候変動に具体的な対策を |
|
| 目標15: 陸の豊かさも守ろう |
|
| 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう |
|
多様なステークホルダーとの協働
双葉町の復興は、行政だけでなく多様なステークホルダーとの協働によって進められています。これはSDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を体現するものです。
住民参加と協働
避難先にいる町民も含め、住民の声を復興に反映させる取り組みが行われています:
- オンラインも活用した住民説明会や意見交換会
- 復興計画への住民意見の反映
- 町民によるワーキンググループの設置
- 若者や女性の視点を取り入れる仕組みづくり
自治体間連携
近隣自治体や全国の自治体との連携も復興の大きな力となっています:
- 双葉郡8町村による広域連携
- 全国の自治体との相互支援協定
- 避難先自治体との継続的な協力関係
- 共通課題に取り組む自治体ネットワークへの参加
国際的な知見の活用
国際的な災害復興やSDGsの知見も積極的に取り入れられています:
- 国連機関や国際NGOとの連携
- 海外の災害復興事例の研究
- SDGs推進に関する国際的なベストプラクティスの活用
- 復興経験の国際的な発信
持続可能性の評価と将来への展望
双葉町のSDGsを基盤とした復興の進捗は、定期的に評価され、必要に応じて計画が見直されています。
復興の進捗管理
復興計画の実施状況を客観的に評価するため、以下のような取り組みが行われています:
- SDGsの指標を活用した復興進捗の可視化
- 定期的な住民アンケートによる満足度調査
- 環境モニタリングデータの継続的な収集と公開
- 復興事業の定期的な評価と見直し
長期的な展望
双葉町は、単に震災前の状態に戻すのではなく、より持続可能な未来に向けたビジョンを描いています:
- 2030年のSDGs達成年を見据えた計画の策定
- 人口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくり
- 気候変動など将来のリスクに備えたレジリエンスの強化
- 次世代に継承できる持続可能な地域社会の構築
まとめ:SDGsを通じた創造的復興のモデルとして
双葉町の復興は、単なる災害からの復旧にとどまらず、SDGsの理念に基づいた「創造的復興」を目指しています。被災地としての厳しい現実に直面しながらも、環境・社会・経済の三側面から持続可能性を追求する双葉町の取り組みは、他の災害被災地や持続可能なまちづくりを目指す地域にとっても、参考となるモデルケースとなりつつあります。
原子力災害という未曾有の困難に直面しながらも、「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念に沿って再生を図る双葉町。その挑戦は、災害からの復興とSDGsの実現という二つの大きな課題に同時に取り組む先駆的な事例として、国内外から注目されています。
双葉町の復興はまだ途上であり、多くの課題が残されていますが、SDGsという世界共通の目標と連携することで、地域の再生と地球規模の課題解決を結びつける新たな道を切り拓いています。


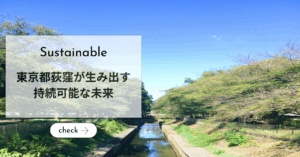





コメント