【地熱発電を再考】異分野の知見が拓く地域合意の突破口
地熱発電は、天候に左右されないクリーンエネルギーとして注目されながらも、温泉組合など地元住民の反対を受けやすく、開発に長期間を要するケースが多いのが現状です。東北大学の鈴木杏奈准教授らは、この「定説」をくつがえすべく、哲学や脳科学の知見を用いて価値観の違いを越えた合意形成方法を模索しています。本稿では、最新の取り組み事例と背景を整理します。
1. 地熱開発を阻む「価値観のギャップ」
従来の合意形成の問題点
技術導入時、行政は「技術が理解されれば受け入れられる」と考えがちですが、実際に反対する地元住民は高度な専門知識を有していることが多く、単なる情報提供だけでは合意は得られません。
哲学が示す「3つの価値観」
アメリカの哲学者C.S.パースの「探求理論」によれば、いかなる議論も**論理(Logic)/倫理(Ethics)/美学(Aesthetics)**の3要素で成り立っています。技術者は論理を重視しがちですが、住民の反対意見には「この地域の自然はこうあるべきだ」という倫理や「景観の美しさを守りたい」という美学が根底にあります。これを無視して論理だけをぶつけても、合意は得られません。
2. 脳科学が示す「非日常体験の場」
対話を円滑にする場づくり
脳科学の研究では、新しい情報を受け入れやすい状態をつくるには「非日常的な体験」が有効とされます。緊張感のない環境で、肩書きを外した自由な対話空間を設けることで、相手の価値観にも耳を傾けやすくなるのです。
「ワクワクアズライフ」の事例
鈴木准教授が手がける「ワクワクアズライフ」では、温泉旅館を貸し切ったツアーを通じて「地熱の楽しみ方」を体感。参加者同士が立場を越えて交流し、地域資源への共感を醸成することで、対立ではなく“ごった煮”の協働基盤を築いています。
3. 技術革新と地域共創の両輪
開発期間を短縮した事例
スーパーマーケット「業務スーパー」創業者の沼田昭二氏は、自走式掘削機の独自開発により、通常10年以上かかる地熱発電所を約5年で運転開始。技術面だけでなく、地元との継続的な対話を重ねたことが成功要因です。
低温熱利用の拡大
アイスランドでは、発電に適さない低温熱水を配管で各地へ送って暖房に活用し、国全体の暖房需要の約90%を賄っています。日本でも一部地熱発電所で「段階利用」を検討する動きがあり、資源を余すところなく活用する発想が広がりつつあります。
4. 今後の展望
地熱発電は、安定した大容量電力を供給できる魅力的な再エネ資源です。哲学や脳科学に裏打ちされた合意形成手法と技術革新を組み合わせることで、従来の「開発難航」という定説を覆し、世界3位の地熱ポテンシャルを本格的に活用する道が拓かれつつあります。


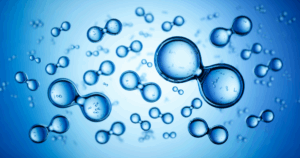





-300x158.png)

コメント